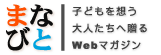美・知との遭遇 美術教育見聞録 学び!と美術
自然の息吹を
教え、伝える勇気を持って

自然の息吹を忘れた子どもたち
ウジャウジャとした生命の大集合体(動物に限ってですが)を目にしたことがありますか。少なくとも人の数よりも生き物の数の方が多いという場面は、近頃あまり目にしなくなったように思います。
たとえば、卵から孵(かえ)ったばかりのおびただしい数のおたまじゃくしの集団を見たことがありますか。また漁港の船から陸揚げされる大量のサンマの集団を見たことがありますか。そういった場面を、大人の私たちですら見る機会が少なくなっています。
オリンピックに集まる人の集団を見たり、毎日通勤ラッシュで人があふれている新宿駅や渋谷駅を見たりする数に比べれば、空を飛ぶ鳩の群れやときどき群れて飛ぶトンボにおいても、目にする動物の数は圧倒的に少ないのではないでしょうか。都市化が進んで、人間は他の生き物を自分のまわりから遠ざけてしまったことにより、人間よりもおびただしい数の生命が集まっているという動物の集団を目にすることが少なくなっています。もっとも簡単に多くの生き物を見ようとするなら、飴玉を地面に放り出しておくといつの間にか集まる蟻でしょうか。
秋のこの時期、雑木林に入ったことがありますか。それは自然の林でなくても構いません。地面が踏みならされたような、訪れる人の多い公園の雑木林の中にもあるかもしれません。茂みの下などの軟らかい土を選んで浅く掘ってみてください。その軟らかな土のほとんどは、ミミズの体内を通った土であることを発見することがあります。その不自然な柔らかい土の下をさらに深く掘ってみると、隙間なく集まったミミズの集団を見ることができます。
また、清流の淵に、ビスケットやパンを細かくして投げてみてください。深みにいた小魚が水面を盛り上げるほど集まるときがあります。
そういう生命の大集団というものを子どもたちが知らなければ、あたかも人間という大集団がこの世でもっとも多い集団であり、自然を圧するかのように君臨していると錯覚しているかもしれません。
私たちは自分のまわりから多くの動物を遠ざけてはきましたが、自然の生命は圧倒的であり、畏敬するほどに強いのです。どんなに私たちが地球環境を破壊しても、そのことによって滅びる生命はすべてではありません。その多くの問題の究極の向こうに「私たち人間が生きていけない」という過酷な現実が待つからこそ、私たちは大変だと思っているわけです。その私たちが、前向きにその事態が解決できると思っているなら大失敗するでしょう。大きな自然に立ち向かうとき、攻撃は最大の防御ではないという心構えが必要です。自然を私たちの力で何とか改善しようとしても、それは元の、本来の自然の状態に戻すほかないことが多いのです。おそらく、大海原の水を電気分解して酸素を大気に放出し、水素をエネルギーに使おうとしても、ごく一部の例えばオゾン層の改善、熱帯雨林の伐採をほんの少し補うだけに過ぎないでしょう。
そういうことの専門家でない私たちが実感として、それを認識するには、やはり自然体験、多くの生命の存在と生命ネットワークというものを直感する以外にないのです。
現代の子どもたち、特に日本の子どもたちが自然から遠ざかっているということは、多くの生命から遠ざかっているということです。この現実は、徐々に先進諸国に広がり、やがてこれから地球上で育つ大半の子どもたちに伝播するでしょう。そのときこそ人類が危ないと思うのです。
勇気を持って教えること
私たちが、絵を描かせたり、粘土という材料を与えたり、デザインという教育をする裏には、教科の中にとどまらない、未来を生きる子どもたちの大きなビジョンの中に、それぞれの教科があるということを忘れてはなりません。平和のためのポスターを描いても、使い勝手の良いペーパーナイフを授業で作っても、そのことを通して私たちが、子どもに感覚させたいこと、子どもに知覚させたいことというのは、ストレートに造形的な内容だけではありません。そういうことを私たちが指導者として自覚しているか、いないかは、その授業に価値があるかどうかということに等しいと思いませんか。
教師によって計画される授業が、1時間に満たない短時間の学習が、15歳までの9年間積み重なることにより、子どもたちの中に何が育つのかということを私たちは自覚し、授業を演出する必要があります。そして、それぞれの教科学習が総合され義務教育を終えるまでに、子どもたちに何を手渡し、社会に送り出すのかということを責任とするべきなのです。単に、教科内容を効率よく上手に教えられることだけが私たちの教師力ではありません。子どもたちが人間関係に悩むとき、進路に迷うとき、そして、未来に向けての志を抱くときに、必ず教師に相談します。それは、たまたま私たちが近くにいる大人なのではなく、深いところで自分たちを見守ったり、将来を心配してくれたり、いい方向を示してくれたりする人であると信じるからです。
私たちが自らの生命で体験してきた半生の学びを担当する授業を借りて、子どもたちに伝えていく役目を担っているのが教師だと思うのです。たとえ、教え諭したことが必ずしも正しくなかったと思われる未来が訪れたとしても、それは私たちの誠意として伝えようとした限りにおいては、時代とともに価値が変化したことや私たちが至らなかったことを、すっかり大人になった彼らは理解するでしょう。
私たちは、常に謙虚に学び続けながらも、教え伝える勇気をもつ必要があるのです。