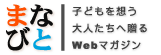大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
ルイス・フロイスが見た日本
自己表現の変化がもたらしたものとは
フロイスの軌跡
 イエズス会宣教師ルイス・フロイス(1532-97年)は、ポルトガル人、16歳でイエズス会に入り、インドでゴアの聖パウロ学院に学び、フランシスコ・ザビエルから日本事情を聞き、日本伝道への志を抱き、1562(永禄5)年にパーデレとして日本に赴任して来た人物です。
イエズス会宣教師ルイス・フロイス(1532-97年)は、ポルトガル人、16歳でイエズス会に入り、インドでゴアの聖パウロ学院に学び、フランシスコ・ザビエルから日本事情を聞き、日本伝道への志を抱き、1562(永禄5)年にパーデレとして日本に赴任して来た人物です。
北九州で布教後、64年に京都に上り、京畿で働き、69年に織田信長に拝謁して厚遇を受けることとなります。78(天正6)年からは豊後の大友義鎮のもとで4年間を過ごし、81年には巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノが信長と会見した際の通詞を務めた。86年には大坂城で豊臣秀吉の歓待を受けましたが、87年の「伴天連追放令」後は加津佐・長崎などに在住し、96(慶長元)年11月には長崎で「26聖人殉教」を目撃し、その年65歳で歿しました。
フロイスは、イエズス会の宣教師として、文書記録を担っていたようで、日本宣教の詳細な報告書を認めたのみならず、『日本史』で同時代の政治経済情勢のみならず、日本の思想・宗教・文化・社会、生活風俗を具体的に描いています。
1992(平成4)年に放映されたNHK大河ドラマ「信長 King of Zipangu」(Vol.025 3月号2009)、は『日本史』を素材にフロイスの目を通して描いたものです。ここに紹介する『日欧文化比較』は、1585(天正13)年に加津佐でまとめられたもので、日欧の衣食住をはじめとする生活文化から信仰習俗の差異を比較対照して簡潔に認めたもので、日本理解の手引書にほかなりません。こうした日本への目は、ザビエルが日本布教を日本人に合わせる順応策となし、日本に派遣する宣教師に、日本語の習得と日本の生活や文化を学ぶことを課したことによります。
日本に派遣された宣教師は、ここにまとめられた世界をマカオの神学校で学び、ついで日本に着任する中で身につけた知識をふまえ、日本の生活文化に寄り添いながら日本人の心を開く営みをなし、イエスが説いた福音-隣人への愛の実践-を戦乱の巷で生きる糧として問いかけました。この働きかけこそは16世紀を「キリシタンの世紀」となさしめたものにほかなりません。
フロイスは、宣教の実践で直面した日欧の生活文化の落差を直裁に問い質し、「ヨーロッパの人々の習慣とこの日本の国の人々の習慣との間にある若干の対照と差異について述べた小冊子」と冒頭に記していますように、日本の日常的な生活風俗をきわめて具体的に描いています。そこには、日本人にとってみればきわめて日常的で当たり前のことだけに、はじめて気付かされる世界が読みとれます。それは、観念の比較文化でなく、日常卑近に見聞した世界にほかなりません。
まさにフロイスの問いかけは、己と異質な他者に対する日本人の身構えであり、自己防衛の一形態でもある仕草を媒介に日欧の比較対照をなし、日本文化の深層構造を解析する素材となります。
男と女の表情をめぐり
- ヨーロッパ人は大きな目を美しいとしている。日本人はそれをおそろしいものと考え、涙の出る部分の閉じているのを美しいとしている。
- われわれの間では白い目を奇異に思うことはない。日本人はそれを奇怪に思い、彼らの間では希有のことである。
- ヨーロッパでは、顔の化粧品や美顔料がはっきりと見えるようでは、不手際とされている。日本の女性は白粉を重ねる程、一層優美だと思っている。
日本では、男女ともに表情をあらわにすることを嗜みのない者として軽蔑されます。喜怒哀楽を押し殺し、いかなる状況でも泰然自若としているのが男とみなされてきました。心があらわに出るのは修養が足りない証にほかなりません。日本人の「無表情」は儒教が説き聞かせてきた修養の論理が心身に刻みこまれてきたが故です。そのため相手を知るには、「胸の内をさぐり」、「腹を読む」ことが求められたのです。「白眼視」「白い目で見る」という表現は、ヨーロッパにないもので、他者を貶める一つの作法です。目が合うことは、「眼(がん)をつけた」なる「言いがかり」があらわすように、人間関係で緊張が走る場面です。
日本女性の化粧法は、白粉を厚くぬり、目と口を小さく描きます。それは、喜怒哀楽が表情に表れるのを無作法、「はしたない」行為とみなしたことによります。幕末日本に幽閉されたロシア人ゴロウニンは婦人の無表情な容貌を「死人」のようだと述べていますが、武家などの上流婦人の化粧法は「死化粧」といわれるものでした。それは、白粉を厚く塗り、口紅を挿した唇が笹色となったことによります。この「笹色紅」は、無表情な「死化粧」を演出し、武家婦人のたしなみとみなされていました。
その一方、元禄頃からは、白粉など塗らないで、紅を挿すだけの町娘が登場します。こうした町娘の「素化粧」は、浮世絵に描かれましたが、「蓮っ葉女」とみなされたのです。いわば「死化粧」が物語る表情やしぐさ、化粧作法には、人欲の否定を是となし、修養を説く儒教的モラルに囚われた日本人の身体観が直裁に読みとれます。
「無表情の美学」の果てに
ここにみられる「無表情の美学」は、明治の文明開化にはじまる日本の近代化がいかに急速に展開されようとも、日本国民の心を呪縛しておりました。戦死者の母や妻には、人前で涙を見せることが恥とされ、「健気」に耐え忍ぶことが「愛国の作法」として求められました。この心身を密封してきた日本文化の構造こそは、西洋人のみならず外国人が「顔のない日本人」と揶揄し、日本人の無表情が再々話題とされてきた根にある世界です。
日本人の身体表現がこうした「無表情」の帳を脱却するのは、1945年の敗戦を経て、1960年代の高度経済成長がもたらした生活、消費文化の展開を待たねばなりません。
かくて女性は、己の「個性」を化粧で表現し、「羞恥心」なる言葉を掃き捨て、他者の存在を顧みない「勝手気儘」な振る舞いを自己表現とみなすこととなったようです。
昨今は、男も女も「無表情」を何よりも嫌悪するかのごとく、「あからさま」に己をさらけ出すのが「美学」と心得ている節があります。いわば心身の開放は、所かまわず化粧に励み、肌をさらし、男女を問わずアクセサリーを身に着けるなど、他者との差異性を主張するのが自己主張であると思いみなす文化を生み育てているのではないでしょうか。そこに展開する様相には、お互いが了解しあえる協同社会が崩壊し、他者を他者と意識せず、身に纏った鎧を脱ぎ捨て、勝手放題にふるまうことが許された小宇宙をして、世間一般の風潮となさしめたとの観すらうかがえます。
ここにある落差を読み解くためには、ルイス・フロイスをはじめとする来日外国人の眼が日本と日本人をどのように見つめていたかを解析し、日本人の自画像を己の眼で確かめて見ることが問われているようです。
 ヨーロッパ文化と日本文化
ヨーロッパ文化と日本文化
ルイス・フロイス 著
岡田章雄 訳注
1991年 岩波文庫 刊