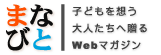美・知との遭遇 美術教育見聞録 学び!と美術
種火となる生命の体験

ひなびた漁村の田舎町で生まれた私は、幼少期の思い出はというと、その多くが海や川そして雑木林の風景とともにあります。ゆったりと時間の流れていた幼い頃の輝く日々を振り返ると、生きた実感がもっとも強く感じられた頃であったように思います。
その頃は、各家庭にテレビもなく、塾通いも希でした。土曜日以外の普段の日にも、学校を終えたあとは十分な遊ぶ時間があり、異年齢の悪ガキ集団が形成されていました。ランドセルを自宅の居間に投げ出すと、お決まりのように河口近くの川べりに遊びに出かけます。そこには、年齢が近いと思われる二人の老人が、雨の日以外は必ずといっていいほど定位置にいたのです。二人はそれぞれお決まりのポーズでしたから、遠くからでもどちらの爺ちゃんかを見間違うことはありませんでした。
一人は、不安定なパイプ椅子に腰掛けてガードレールにもたれかかりながら、遠くを見るような細い目をして河口から海の方を見ていました。もうずいぶん前に漁に出ることができなくなってしまった元漁師の爺ちゃんです。夜の漁りにでる準備で忙しい漁港の喧噪の中、息子たちが船出するのを眺めているのだということを私たちは知っていました。子どもにはけっしてやさしくなく、声をかけてもろくに返事もしませんでした。子どもらが周辺で騒いでいても興味ありそうな顔一つせず、飽きずに海を眺めていました。その老人は、本来はけっして子ども嫌いではないと、幼心に感じていました。
もう一人の老人は、大水の時に川を流れる流木を集め、それを乾燥させてから割り、タキギ束をこしらえていました。休日などには、山の畑で見かけることもあったのですが、川べりで子どもらに会うと、お決まりのうさん臭い顔をして、黙々と薪割りをしているのです。しかし、その老人も私たちを嫌ってはいないと思っていました。太い丸太や複雑な枝ぶりの木が、いつの間にかすべてタキギ束になってきれいに並べられていくのを身近で観察していました。
二人の間には時々、あいさつ程度の会話があったように記憶していますが、ほとんどの時間が寡黙の中に流れる10メートル程の距離でした。子どもたちにとって、自然とともに遊び、街中で探偵ゴッコをしていた当時の思い出深い情景であったと思われます。二人の考えていることは私たちには分りませんが、迷い無く生きる知恵を持った人間のベテランのように感じていたのでしょう。
その老人たちは、休息時などに細長い古びたキセルを取り出しタバコを吸うのです。刻みタバコを詰め、手と口でキセルを支えながらマッチで火をつけるまでの一部始終を何度か見ていたように思います。多くの記憶が忘れ去られた中でも、この意味の無いような記憶だけは鮮明に残されているのです。いつもそうした情景の中で暮らしながら、だれに言って聞かされたわけでもなく、互いに話し合うことがあるわけでもなく、子ども各自がその情景をそれぞれに認識し、何かを学んでいたような気がします。生命と生命が出会う環境のひとつとして、その場所の風景があったようにも思われます。
あの頃から半世紀近くを経て、時代が子どもたちの体験の場を大きく変容させてしまいました。知識の学習や知恵の伝承は成長したあとでも間に合うものですが、子どもならではの感受性で踏みしめるように味わってきた感性の蓄積は、その時々だけがチャンスなのだと思います。都市化された社会の中で、子どもたちは、自分で生きていると実感することを奪われてしまっている時代なのかもしれません。自分が生かされていると感じる対象が家庭や社会であったなら、依存心から生じた日々の不満をその対象に蓄積させるだけのように思えてなりません。
故郷を離れてしばらくして、海を見つめる老人も薪割りをする老人も、もうこの世の人でないことを知らされました。小学生の頃の体験が種火として残っていて、成長した私の心で一瞬大きく燃え盛ったような感覚がありました。
その後も、私の記憶とともにあるかけがえのない人やモノが現実から消えていきました。記憶と同じ場所に立つことはできても、貴重な思い出となった「時」や「人」が戻らないことを悟る体験だけが私に残されました。私たちは、誰とも同じではない生命の軌跡をもっています。生きた長さに比例して、共有部分が多いと思われる認識が生まれ、個性が際立つと思われる価値観などが複雑に形成されていくのではないでしょうか。そのいずれかが主題となって表現された時、それぞれに感じ合うところに表現の喜びがあるように思います。私も雑務の忙しさにかまけて、しばらく表現することから遠ざかっている自分に反省をしなければなりません。