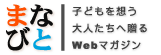大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
続・「忠臣蔵」という物語
閑話休題
 浅野の殿様は吉良を背後から切りつけました。相手に挑むなら、前から刀を突き刺すのが常道。この作法に悖る行為。こうした浅野の吉良討ちは武士としていかがなものかと話題となり、「忠臣蔵」が武士の鑑と喧伝される一方で、内匠頭が吉良を背後から襲ったことをどう武士道の論理に位置づければよいかが、世の識者を悩ませることとなります。
浅野の殿様は吉良を背後から切りつけました。相手に挑むなら、前から刀を突き刺すのが常道。この作法に悖る行為。こうした浅野の吉良討ちは武士としていかがなものかと話題となり、「忠臣蔵」が武士の鑑と喧伝される一方で、内匠頭が吉良を背後から襲ったことをどう武士道の論理に位置づければよいかが、世の識者を悩ませることとなります。
乃木希典も赤穂浪士に武士道の姿を想いみた一人だけに、このことにこだわっています。しかし「義士」論では正面から殿を問い質すものがありません。「義士」を時代社会にどのように位置づけるかというイデオロギーの問題であり、赤穂の浪士を非とすること憚る風潮が明治の御世以後の世間の気分となっていたといえましょう。さて、その論争はいかに。「忠臣蔵」美談ともいうべき記憶はどのようにして日本国民に刷り込まれたのでしょうか。
「義士」をめぐる論争
浪士を義士と賞賛する声は、伊藤東涯が『義士行』の長詩で、浅海綗斎(けいさい)
が「四十六人の輩、忠義の大要はまぎるる事なし」と『赤穂四十六士論』で主張しました。水戸徳川家の彰考館の学者は浪士を支持し、三宅観瀾(かんらん)は『烈士報讐録』で顕彰します。
その一方、荻生徂徠は『赤穂四十六士論』『徂徠擬律書(そらいぎりつしょ)』で「義央、長矩を殺さんとせしに非ず。君の仇と言うべからざるなり」としたうえで、「主人のために讎をほうじたのは侍たる者の恥をしっており、己を潔くする道にして、其事は義であるとはいえ、其党に限る事なれば、畢竟は私の論」「私論を以て公論を害せば、此以後、天下の法は立べからず」と論じ、弟子の太宰春台は『赤穂四十六士論』で、「吉良は赤穂の仇なのか」と問い、「仇にあらざるを仇とす。妬婦の情に類せずや」と批判しています。佐藤直方も『復讐論』で吉良が仇ではないと論じています。当代の儒者は、事件を前にして、己の学問を問われたといえましょう。
まさに事件は、武断政治から法と礼を規範とする文治政治がもたらした徳川の平和に棹をさすものだけに、「戦士」たる者の志を武士の代の規範にどのように位置づけるかが問われたのです。世間は、戦国の余風が治まった天下泰平の世で、戦国の余燼を見る想いにたじろぎ、多くの武士が事件で死に、切腹したことに驚きました。しかも「平和」な当世に主君の仇を討った戦士が登場したとなると、世に説かれる武士の道義、士道を眼前に見る想いを地でいった物語として好奇心をつのらせました。ここに物語は、当世風にいえば事件記者的な好奇心がテレビの話題となるように、きわもの嗜好よろしく歌舞伎や浄瑠璃の舞台を彩ります。
また外国人の眼は、元禄16(1703)年、浪士切腹の年に入貢したオランダ商館長ハルデナントス・デ・ゴロウトの見聞をもとに、日本の君臣間の「忠誠の鏡」と紹介しております。「忠誠」の物語との思いは、第26代アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの親日感情となり、日露講和の仲介者に成さしめました。その意味では、「騎士道」につらなるものとして、「忠臣蔵」に日本武士道の幻想を読みとり、ある日本像が造型されたのだといえましょう。それは新渡戸稲造の『武士道』を受けとめた下地ともなります。
上演された物語
1703(元禄16)年2月、浪士切腹後の16日から、曽我兄弟の仇討ちに仮託した「曙曽我夜討(あけぼのそがのようち)」が江戸の中村座で上演されたものの、3日で禁止されました。そのため、この事件を題材としたのは、事件から4年後の1706(宝永3)年、浄瑠璃「碁盤太平記」を待たねばなりません。太平記に仮託した事件の語りはここにはじまります。舞台をささえた大衆の気分は、儒者の議論にかかわりなく、浪士は義士、忠臣であり、善玉として描かれています。これが「義士伝」「忠臣蔵」の基本形となります。
そして討入りから47年目の1748(寛延元)年に「仮名手本忠臣蔵」の上演。それは、討入り後に姿を消し、生き残った47人目の「志士」とも称されることとなる寺坂吉右衛門が死んだ翌年のことです。ちなみに、寺坂は大石が討入り成功後に逃がし、成功の報を芸州浅野家など伝える旅に出したといわれています。この行為は、寺坂に赤穂の浪士の吉良討ちの行為にこめた意図を広く天下に喧伝し、徳川の御政道を質そうとした大石良雄の遠大なる謀という「神話」となります。
「仮名手本忠臣蔵」こそは、いろは47文字にあて、四十七士を描き、現在にいたるまで上演され続けています。
かくて「忠臣蔵」が一人歩きをし、「義士」像には時代の思いが託され、さまざまな「忠臣蔵」が文学作品や映画となり、TVドラマとして、年の瀬の話題となり、世間の注目を集めております。
小説、映画、テレビのなかで
「忠臣蔵」なる名称に仮託された忠義の物語は、武士道鼓吹の尖兵として、軍国日本の魂の物語、日本精神の精華として時代の装飾に彩られて語られてきました。この位置づけは、江戸に行幸した明治天皇が1868(明治元)年11月5日に勅使を泉岳寺に差遣して勅旨を述べ、金幣をとどけたなかに近代日本の精神のありかを読み取れます。まさに天皇は、維新政府に始まる日本国家は、赤穂の浪士の行為を「義挙」とする論功行賞を行い、「仮名手本忠臣蔵」に呼応した民の心に寄り添うことで国家の精神の造形をはじめたといえましょう。かくて浪士の復讐譚は、「忠臣蔵」となり、己が主君に報いる精神の物語として唱和されたのです。その歌は、世間に認められず世に入れられぬ敗者の美学を奏でるものとして裏声でうたわれる世界でもありました。
忠臣武士道の世界は、日露戦争後の忠君愛国熱を背に武士道節で一世を風靡した桃中軒雲右衛門の浪花節が忠臣蔵で人気を博しました。義士の事績は、福本日南の『元禄快挙録』(1909年)が「義士」像の決定版として、世間の評判を呼びました。義士の切腹は武士道の精華とされ、日本人の腹切りとして世界に喧伝されます。しかし赤穂浪士の切腹図は皆苦痛で顔をゆがめています。士道を体現し見事などといえるものではありません。ここに浪士たる生身の人間の姿があります。
こうした生身の人間を現在の物語にしたのは、「義士」像にひそかに異議を唱え、義士ではなく浪士としての大石一党を描いた大仏次郎『赤穂浪士』(1927年)です。この作品は、後にNHK大河ドラマ「赤穂浪士」として街の話題を呼びましたが、昭和初頭の不安な世相を背景に失業武士たる赤穂の浪士の吉良邸討入りにいたるドラマが描かれています。
ついで船橋聖一『新忠臣蔵』(1957-61年)は大河ドラマ「元禄繚乱」の原作ですが、昭和元禄の気分になぞり復讐譚にみられる人間模様が権力をめぐるドラマとなっています。最近のものでは、池宮彰一郎『四十七人の刺客』(1992年)、ついで『最後の忠臣蔵』、改題『四十七人目の刺客』(1997年)等々がありますが、各作品には時代の空気が投影されており、大石良雄ら赤穂の浪士に託した現在を生きる作者の思いが描かれています。
このような目で作品にふれ、「義士」なる世界を問い質したとき、日本と日本人が「忠臣蔵」なる物語に寄せねばならなかった哀しき自画像が見えてくるのではないでしょうか。