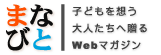大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
ふるあめりかに袖はぬらさじ ―喜遊哀歌―
岩亀楼喜遊のこと
文久2(1862)年11月23日、横浜港崎(みよざき)遊廓の岩亀楼(がんきろう)の遊女喜遊が「アメリカ人アボット」を客とするのを拒否、武士の作法による切腹をして果てました。その辞世が攘夷の気分をもりあげ、世に喧伝されていきます。
露をだにいとふ倭の女朗花
ふるあめりかに袖はぬらさじ
この辞世とともに次のような内容からなる一通の遺書があったといわれています。
いかで日の本の女の操を、異人の肌に汚すべき。わが無念の歯がみせし死骸を、今宵の異人に見せ、かかる卑しき遊女さへ、日の本の人の志はかくぞと知らしめ給ふべし
喜遊の死体は、翌24日早朝に奉行所の調役杉浦竹三郎、刑部鐡太郎、長岡鎭太郎による出張検死後、焼却、遺骨はどこに埋められたか不明。
喜遊は、箕部周庵なる江戸の町医者の娘。文久元年18歳とあることより、弘化元(1844)年生。自殺した時が19歳。本名が喜佐子。父周庵は、尊皇攘夷の志かたく、文久元年5月の高輪東禅寺のイギリス公使館に水戸藩士ら14名が乱入した事件の関係者として捕縛され、医業を禁止の上、江戸追放となります。品川に住んだ父娘は生活に窮迫し、父周庵の病により債権者に追われる日々がつづきました。
かくて娘喜佐子は、北品川宿名主佐次平にはかり、同人兄佐吉が経営する横浜岩亀楼に遊女として身を売ったのです。約定金は300両、「断じて、異人を客に取らせぬ」という条件。ここに父周庵は、名主佐次平の鮫洲の別邸に引きとられて療養します。娘喜佐子は、源氏名を喜遊と名のり、文久2年正月より岩亀楼で店に出たといいます。
米人アボットをめぐり
喜遊の客アメリカ人商人アボットは幕府と関係あるフランス商人アポネであったといわれています。幕府は、横須賀造船所の建設にフランスの援助を受けましたように、武器弾薬をフランスより輸入しようとしています。これに応じた商人がアポネでした。そのためアポネは、幕府とフランス公使の間を周旋するなど、フランスからの借款問題もあり、江戸の幕閣とも特別な関係をもっていたといわれている人物です。
横浜の地は、異人相手の遊女や素人のラシヤメン(洋妾)の間でアメリカ人の人気が高かった地です。そのためアポネは、幕府との関係を隠して遊ぶため、人気にあやかり「アメリカ人アボット」を名乗りました。
岩亀楼は異人客専門の3階洋風建築(異人館)と日本人客専門の2階作りの和風建築(日本館)との2棟からなり、遊女も異人相手と日本人相手の二種に別れていました。客の混同は神奈川奉行によって厳しく禁じられていたそうです。日本館の遊女は、横浜沖に碇泊中の黒船に行く「黒船夜鷹」などを前身とする者が多く、異人館と比べて見劣りがした女たちでした。
喜遊は、日本館の日本人専門の遊女で、売出した日から評判高く、琴、三味線、茶道、生花、和歌などの芸事に通じた女であったといわれています。そのためアポネは、異人館の遊女ではなく、日本館の上品な遊女、その第一と称された喜遊と絜を結ぼうとします。その思いは喜遊に拒否されたがため、神奈川奉行からの強要となったのです。「如何にも、かの異人を客とすべし」との命を前に、喜遊は切腹することで己の志を貫いたといえましょう。
憤死の波紋
喜遊の死は、文久3年1月13日発行の上海の英字新聞で報じられ、幕府の秘匿にかかわらず上海情報として語られていきます。ここに噂が噂をよび、喜遊の切腹がペリーの強要した開国がもたらした世情不安の波にのり、攘夷の心情を巷に渦まかせたのです。しかも文久3年の攘夷決行という狼煙は、喜遊の辞世「ふるあめりかに袖はぬらさじ」が攘夷派の心情を吐露したものとして、人口に膾炙(かいしゃ)し、攘夷の風が世間を覆ったのです。
ちなみに、この歌は、文久2年正月、老中安蒔信睦を坂下門外に襲撃した浪士の一味なる大橋訥庵かその門人の椋本京太郎の偽作で、攘夷派の志気を高めるために、喜遊の事件に託したのだとも言われています。ここには、黒船の砲艦外交に強要された開国下の鬱屈した民衆の心情が読み取れます。まさに歌に込められた思いこそは民衆の心の底に潜む素朴なナショナリズムにほかなりません。このことは、日本の対米関係が緊張をはらむたびに、ある種の反米、嫌米感情を表す言説として「ふるあめりかに袖はぬらさじ」なる歌が広く世間に流布していることにも伺えます。文学座の公演もその一つであり、国会でも、米軍基地における米人の犯罪にかかわる審議の際、日本の法の執行が及ばない米軍基地問題に関わらせ、自嘲気味に喜遊の辞世が口走られています。
岩亀楼喜遊の辞世をめぐる記憶こそは、文久3の年攘夷決行前夜の時代人心をこえて、強大なアメリカの力に対する鬱鬱たる思い、日本民族の血を騒がすナショナルな気分を突き動かすパン種といえましょう。思うにナショナリズムとは、こうした情緒に促され、奔流となってほとばしりいくパトスに他なりません。それだけに民族の記憶とされた世界を己の目で問い質すことが現在(いま)ほど求められている時はないのではないでしょうか。