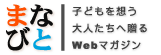大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
楠正成像に読みとる時代精神
楠公信仰の下で
 楠公信仰は、湊川の戦で死んだ南朝の忠臣楠正成の忠誠心を賞で、楠公に殉じんとの想いがもたらしたものです。頼山陽は、『日本外史』で桜井の遺跡が忘却されていることに人心の荒廃を読み取り、楠氏の事跡を説き、「七生報国」に生きようとした楠公を歴史に復活させ、日本の国のかたちが尊皇の歴史にあると説きました。ここに『日本外史』は、開港がもたらした外冦(がいこう)の危機を憂うる志士に、藩という枠をこえた日本という国のあり方を自覚させる書となり、日本の歴史への目を用意したのです。しかも太平記読みが説く『太平記』の世界は、諸葛孔明にも匹敵する正成の知略を広く世間周知のものとしていただけに、「七生報国」に生きた楠氏一党の事跡が幕末動乱を生きる庶民のみならず、明日を切り拓かんと討幕に駆せ向かう志士の心をとらえました。
楠公信仰は、湊川の戦で死んだ南朝の忠臣楠正成の忠誠心を賞で、楠公に殉じんとの想いがもたらしたものです。頼山陽は、『日本外史』で桜井の遺跡が忘却されていることに人心の荒廃を読み取り、楠氏の事跡を説き、「七生報国」に生きようとした楠公を歴史に復活させ、日本の国のかたちが尊皇の歴史にあると説きました。ここに『日本外史』は、開港がもたらした外冦(がいこう)の危機を憂うる志士に、藩という枠をこえた日本という国のあり方を自覚させる書となり、日本の歴史への目を用意したのです。しかも太平記読みが説く『太平記』の世界は、諸葛孔明にも匹敵する正成の知略を広く世間周知のものとしていただけに、「七生報国」に生きた楠氏一党の事跡が幕末動乱を生きる庶民のみならず、明日を切り拓かんと討幕に駆せ向かう志士の心をとらえました。
![皇居前、楠公銅像(場所は皇居外苑[日比谷濠、馬場先口])](pics/vol003_04.jpg) すでに1835(天保6)年の楠公五百年祭が大国隆正などの国学者の参加で盛り上がっており、「七生報国」の念を遺言状に認め、子息に楠正成のような忠臣になれと諭す者がでるほどでした。長州藩や薩摩藩では楠公祭がもたれ、各地の地誌研究では南朝の遺跡がとりあげられました。こうした動向は、太平記読みの流行とも相まって、南朝顕彰運動をうながしたのです。吉田松陰は松下村塾で「七生説」を説き聞かせます。
すでに1835(天保6)年の楠公五百年祭が大国隆正などの国学者の参加で盛り上がっており、「七生報国」の念を遺言状に認め、子息に楠正成のような忠臣になれと諭す者がでるほどでした。長州藩や薩摩藩では楠公祭がもたれ、各地の地誌研究では南朝の遺跡がとりあげられました。こうした動向は、太平記読みの流行とも相まって、南朝顕彰運動をうながしたのです。吉田松陰は松下村塾で「七生説」を説き聞かせます。
ここに討幕の志半ばで非業の死をとげた志士の追悼は、楠正成の誠忠に報いるためにその命日に営まれた楠公忌に託し、京都東山の地で招魂祭が営まれました。そこでは「七生報国」が讃えられます。この営みは、維新後に京都の河東操練場でペリー来航の1853(嘉永6癸丑)年以後の殉難者の招魂祭となり、京都招魂社の創設につながります。京都招魂社は、1879(明治12)年に伏見戦以後の戦死者を祀った東京招魂社に合祀され、靖国神社にとりこまれました。なお現在京都東山にある霊山護国神社は京都招魂社につらなるもので、その境内には討幕に斃れた志士の墓所があります。
『日本外史』という世界
![大楠公御墓所墓碑(嗚呼忠臣楠子之墓[ああちゅうしんなんしのはか])](pics/vol003_01.jpg) 幕末に生きた志士は、欧米列強の重圧下、日本列島を一つにする国のかたちとは何かに想いを馳せたとき、『日本外史』が説く尊皇という歴史を担う国と提示された世界に明日の日本の姿を見出します。尊皇の志に生きた代表こそは、「七生報国」に己を託し、湊川合戦に赴いた楠正成でした。ここには、歴史に生きることで、己の志を貫こうという激しき思念があります。この思念は、水戸光圀により、湊川の地に「嗚呼忠臣楠氏之墓」を建立せしめました。この楠氏の墓所こそは、幕末に明日の日本を想う志士の心をとらえ、楠公の志につらならんとの念をうながします。
幕末に生きた志士は、欧米列強の重圧下、日本列島を一つにする国のかたちとは何かに想いを馳せたとき、『日本外史』が説く尊皇という歴史を担う国と提示された世界に明日の日本の姿を見出します。尊皇の志に生きた代表こそは、「七生報国」に己を託し、湊川合戦に赴いた楠正成でした。ここには、歴史に生きることで、己の志を貫こうという激しき思念があります。この思念は、水戸光圀により、湊川の地に「嗚呼忠臣楠氏之墓」を建立せしめました。この楠氏の墓所こそは、幕末に明日の日本を想う志士の心をとらえ、楠公の志につらならんとの念をうながします。
後に同志社大学を創立した新島襄はその一人です。新島は、1862(文久2)年12月に湊川の地を訪れ、楠氏の墓碑を読み、「ますます感じ、涙流さぬばかり」であったと日記に認めています。かくて1864(元治元)年5月、新島は攘夷の志にうながされ箱館より「夷情探索」のためアメリカに密出国します。楠公につらなろうとの激しき志は、書斎に墓碑の拓本をかかげているように、キリスト者新島襄の終生かわらぬものだったのです。この旧邸は、京都市上京区寺町にあり、同志社が管理しており、文化財となっています。
 維新政府は、こうした討幕運動の地下水脈を形成した精神文化の潮流をとりこむことで、国家秩序を確定していきます。湊川の楠公墓所には、太政官布告により楠社造営が始まり、1872(明治5)年に別格官弊社湊川神社が成立します。また南朝の遺臣を祀る神社としては、その故地に、菊池神社(菊池武時)、井伊谷神社(宗良親王)などが造営されていきます。
維新政府は、こうした討幕運動の地下水脈を形成した精神文化の潮流をとりこむことで、国家秩序を確定していきます。湊川の楠公墓所には、太政官布告により楠社造営が始まり、1872(明治5)年に別格官弊社湊川神社が成立します。また南朝の遺臣を祀る神社としては、その故地に、菊池神社(菊池武時)、井伊谷神社(宗良親王)などが造営されていきます。
内村鑑三は、1894(明治27)年7月に箱根で開催されたキリスト教青年会の第6回夏期学校における講演『後世への最大遺物』で、後世に何を遺すか、如何なる志をもって生きるかを問いかけます。そのなかで、思想を遺す仕事をした人物として、「勤皇論」を説いた人として頼山陽を紹介し、「山陽の日本外史が日本を拵へた」「山陽は其思想を遺して日本を復活さした」と述べます。
楠公銅像の造型
維新の原動力には、山陽の『日本外史』があり、楠公に託して噴出したラジカルな志がありました。楠正成は、そのような志を体現した人物として、時代の闇を生きたのです。その姿は、小学唱歌で落合直文作詞の「青葉茂れる桜井の 里の渡りの夕まぐれ 木下陰(このしたかげ)に駒とめて 世の行く末をつくづくと 忍ぶ鎧の袖の上(え)に 散るは涙かはた露か」と歌われつづけた世界により、日本国民の心身に刻印されました。この身体に刺さった楠公という棘は、国家精神を発動せしめる器となり、ナショナルな国民感情を想起せしめる場となりました。まさに皇居外苑(当時は宮城前)にある楠公銅像はこうした楠公信仰を体現したものにほかなりません。そこには、日清戦争の勝利で昂揚する国家意識が造型されており、皇国日本によせる熱き思いが吐露されています。
この楠公銅像は、1890(明治23)年に住友家が創業200年を祝い、別子銅山で産出した銅で鋳造し、1897年に完成、1900年7月に宮内省に献納したものです。製作には高村光雲(彫刻)、岡崎雪声(鋳造)らが東京美術学校(現東京藝術大学)の総力を結集してあたりました。この楠正成に託された世界は、菊水の紋や「楠公旗文」である「非理法権天」を問い語ることで、「七生報国」に呪縛された皇国日本像が時代を支配したこともあります。それだけに維新革命を先導した激しき志、革命的ラジカリズムの原器として時代の闇を突破した精神のありかを見出した楠公信仰の相貌を歴史に位置づけたいものです。