 |

 |
中学校の情報教育実践例 |
 |
|
 |
 |
IT活用を促進させるのは「安心感」
〜ネットすべきは人の心〜 |
|
| |
|
 |
| 1.なぜ広がらない?中学校の情報教育 |
IT活用が中学校にはなかなか浸透しないと聞く。文部科学省の実態調査でも,コンピュータを活用した授業ができる教師の割合は小学校72%に対して中学校は53%である。私自身も4年前に県の教育センターで1年間の研修を受けるまでは情報教育の言葉を聞いてもコンピュータ・スキルのことだとばかり思っていたくらいである。
時を同じくして,鳥取県では全ての教諭に対して情報教育レベル研修が行われていた。情報教育の基礎から始まり,情報発信やそれに伴ったスキル研修など個々のレベルに応じてとても丁寧に時間をかけて行われた。しかし,現在それが個人の力として定着し,授業に反映されているかというと疑わしいと言わざるを得ない状況だ。
そのような状況を生み出す背景にはいくつかの問題点が考えられる。
まず,情報教育の目的と教科の目的の両方を達成するためのカリキュラムを再編成する余裕がないということが挙げられる。私も研修が終わってからの次の1年間は情報教育という言葉を忘れてしまいそうになるほど日々の授業や生徒指導などに追われる毎日であった。
次に教科担任制の中学校では,例えば理科でITを活用した学習事例を紹介しても,それは教科に特化したものと解釈されがちであるということである。したがって校内研究会を開いても,教科の枠を越えて学校全体で授業づくりについての議論にはなりにくいのである。
先の文科省の調査結果に戻るが,中学校の教科別の活用状況によると,国語や体育,外国語などの授業での活用は理科や数学の場合と比べて低く,50%を割っている。コンピュータ・スキル自体はどの教科の教師も90%前後であるにも関わらずである。本校も以前は一部の教師のみのIT活用であったり,情報教育であったりした。
そのような中,昨年度(H16年度)の一年間で我が校のIT活用や情報教育への意識は格段に進歩した。特に研究指定も受けておらず,スキル的に卓越した職員は33名中わずか2名だけであった。
それでもIT活用や情報教育への理解が浸透していった要因は何か。それは校内の研究題目に情報教育を盛り込んだからである。校内研究には全職員が関わるので,否が応でもIT活用や情報教育について学ぶ機会があったからだと考える。
以降,本校の取り組みを紹介するが,これは他校でも実現可能な取り組みである。情報担当や学年リーダなどの役割が出てくるが,自身の学校では誰にあたるか考えながら読んでいただければよりイメージが鮮明になるだろう。 |
|
|
 |
| 2.課題を共有するしかけ |
「調べる・まとめる・伝え合う」という情報活用の流れはどの教科の学習場面でもあてはまる。今までは校内授業研究会を開いても教科の壁を意識してしまい,ややもすると授業者を誉めて終わりになることもあった。そのような授業研究会は時間の無駄であり,授業改善には結びつかない。
そこで,教科の壁を越える共通言語的な存在の情報教育の視点で授業を見ることができたならば,同じ基準で授業について語り合えると考え,学校長に研究主任として学校を引っ張らせてくれるように直訴した。学校長自身もやっとワープロソフトがやっと使えるスキルレベルのIT初心者だったが,研究のビジョンを説明すると,非常に理解を示して下さり,研究主任を任せて下さった。旗振り役になることで,研究主任という立場から全体に大号令をかけることができるので,私にはそのポジションが必要であった。
しかし,私自身勉強中ゆえ,学校全体を完全にリードして引っ張っていくだけの力量も十分ではない。そこで,金沢大学助教授の中川一史先生に来校していただき,教師の情報教育第一歩の講義をしていただいた。教材でもホンモノを見せることで生徒の関心や意欲は格段に上がるが,これは何も生徒に限ったことではない。日本の情報教育のトップランナーの一人である中川先生の話は,私が説くよりも格段に浸透率は高く,無理を言って来ていただいた甲斐は十分あった。目の前でライブで話を聞くことほどインパクトが強いものはないからである。
案の定,講義を受けた職員からは「情報教育はコンピュータだけかと思ってた。」「これはまさに授業づくりだよね。」と視点が変わったと言わんばかりの感想が多く聞かれた。日本のトップランナーの方の言葉には力がある。その言葉の中に情報活用の実践力で求めているものは「授業づくり」で我々が大切にしている学びのプロセスに他ならないということが職員に伝わったおかげで,IT活用や情報教育への理解に対する第1の壁がかなり取り除かれた。 |
|
|
 |
| 3.外堀を埋める(校務の情報化) |
情報教育の必要性やITを活用した授業づくりについて共通した視点をもつことに関してはある程度できた。では次にそれを行動に移すにあたってできた。では次にそれを行動に移すにあたって第2の障壁となることは何か。
それは個人のITスキルの格差である。職員室LANは整備されてるが,活用している者は数名で,ワープロ・表計算といった日常校務で使うであろうソフトさえもほとんど使ったことがない職員もいた。
そういう職員に職員室LANの有効性やソフトの活用を促しても具体的な目標やイメージがないのにそれ以上の前進は望めない。それゆえ,研究主任として絶えず意識していたことは,とにかく最低レベルのスキルをつけた職員のすそ野を広げることと職員全員を戦力化するということだった。
現実のスキル格差を打開し,全員で研究を前進させるにはどのようなしかけをするか。それは,しなければならない状況にしてしまうのである。それも全員がしなければならない状況となれば,自分だけは何とか真逃れようなんてことは言えなくなる。
全員がしなければならないことと言えば校務であり,全ての教諭に関係する共通業務は通知票の作成であったので,そこにポイントを絞って初心者攻略作戦を立案した。みんながやるからあなたもやりましょうと外堀をどんどん埋めていくのである。ある程度埋まってしまえばたいていどんな人でも重い腰を上げる。
初心者攻略の具体的な策は2つ。通知票のデジタル化と通知票の所見データを職員全員で作るというものである。活用したのはキッズ・ウェアとキッズ・レコード(いずれも株ファースト)というソフトである。
従来,通知票作成は次のような流れであった。
(1)教科担任ごとに評定を出す。
(2)担任から通知票を預かり一人ずつ転記する。これを各クラス行うが,音楽や美術の教師は全校生徒約370名分の転記をするために非常に時間がかかる。
(3)全部評定が入るのは学期末ギリギリで評定の整合性を教務が確認する余裕もないので教科担任に任せていた。
(4)担任はそれに加えて30名の所見を手書きで3〜4行ずつ丁寧に記入する。
(5)行動記録の評定を約20項目について個人毎に評価するのも担任の仕事。
(6)委員会や部活動の名前を記入し,評定も記入することも担任の仕事。
学期末になると特に担任は本当に身を削る思いで通知票を作っていた。時期的なものかも知れないが,やはり教員は時間的な余裕,精神的な余裕をもちながら生徒の前に立たなければ,その反動は必ず生徒にも影響を与えることになる。それを解決する手段が校務のIT化であり,これも校内研究の1つに組み込んでおいたので,こちらが主導権をもったまま活用促進ができた。
では,上記のグループウェアを活用することで実際はどのように改善されたのか。
(1)教科担任は評定を出す。
(2)Excelのテンプレートにデータをコピー&ペーストして職員室サーバに保存すれば評定完了。
(3)教務は随時ファイルを開いて教科毎に評定の整合性を確認。
(4)日々蓄積した「よいとこみつけ」データから担任が3項目だけに絞り,ファイルとして保存。
(5)担当が評定や所見データを印刷し,あとはクリアファイルに入れて通知票は完成。
(補足)「よいとこみつけ」は生徒のよさに出会った職員がその状況を短い文章でサーバに保存し,誰もがそのよさを共有することができるというグループウェアの機能のことである。担任は自分の教科以外での生徒の姿はわかりにくい。しかし,この「よいとこみつけ」により,生徒の様々なよさが蓄積され,それを見ることができるので,より生徒理解が深まるのである。
この改善のメリットは生徒・教師の双方にあった。まず教師についてだが,転記に費やされる時間がなくなり,転記ミスもなくなった。Excelを使ったことがない人もこれを機に使うようになり,スキル面での全体の底上げもできた。
生徒は担任の視点だけで書かれた所見ではなく,様々な職員からよさを見いだされ,それが伝えられるのだから自己肯定観を強めることとなった。
このようにして生徒・教師の双方にメリットがあるということを前面に出し,外堀を埋めて活用促進を行った。 |
|
|
 |
| 4.ピンチはチャンス |
しかし,外堀を埋められてしまった職員にとってはたまったものではなかっただろう。自前のノートPCがない方には,学校のノートPCを貸与したが,初心者にとってはピンチの状態であることに変わりはなかった。そのような状態から早く脱し,ITを活用することに抵抗感をなくすためにはどうすればいいか。少しでも早くITを活用した授業づくりに向かうようにするにはどうすればいいか。
とにかく相手の内発的意欲を大切にするように努めた。たとえ校務とはいえ,今までとは違うスキルを求められるのである。やろうと思ってもすぐにつまずく初心者への対応は迅速・丁寧に行った。ここでの初心者対応のコツは3つ。
(1)ヘルプの要請があればすぐに対応,(2)聞かれたことだけに丁寧に答える,(3)なるべく操作はしてもらう,という点である。相手のピンチはお互いを理解するチャンスである。相手のスキルもわかり,質問に答えながらコミュニケーションがとれるようになる。誰かが困れば自分の仕事を後回しにしてでもサポートを行った。まわりの方はその対応の姿にものすごく信頼感を寄せてくださるようになった。おかげで,研究に関するアンケートをお願いしても期限内に100%提出して下さった。3回アンケートを行ったのだが,3回とも100%回収できた。 |
|
|
 |
| 5.スタイルは遺伝する |
情報リーダとして私が全てのサポートをするのは物理的に無理なので,学年団の中にも情報リーダ的な存在の人を育成することにも務めた(以下学年リーダ)。その学年リーダとしての適応条件は,(1)ワープロ・表計算ソフトはある程度使える,(2)新しいことにも挑戦意欲がある,(3)学年内での人間関係が良好の3点である。その学年リーダと目星をつけた人物にいろいろな情報を提供した。その方の担当教科に関する資料や活用できそうなコンテンツの紹介など,気がついたときにはとにかくである。繰り返しアタックするのだからしつこくならないように,「読んでみてくださいね」「このコンテンツおもしろそうですよぉ」とサラッとである。それで興味を示してこちらに問い直してきたときは一気に釣り上げる。その時の対応は初心者対応スタイルを意識して行った。相手が内発的な動機をもっているうちに授業イメージを語り合い,具体的な授業案にまでこぎつけ,あとはコンテンツを活用した授業を実践してもらう。相談者から一気にITを活用した実践者へとステージをあげてしまう。そういう上・中級者が学年リーダとして各学年団に存在することにより,初心者も近くに頼れる人がいることを自然と認識する。それはすなわち困ったときにすぐに聞ける人がいるという安心感へとつながった。
初心者の方にインタビューをすると,学年リーダの対応スタイルは先に挙げた私の初心者対応スタイルとほとんど同じであった。やはりこのスタイルは,どこかで引け目を感じているIT初心者の苦手意識を払拭するには必要なのだと考える。
図1をご覧いただきたい。校務で使うスキルについての職員の意識調査だが,調査は昨年の11月である。本格始動の5月から数えて7ヶ月足らずで職員のスキルレベルはかなり高くなった。しかも,校内のスキル研修はゼロである。一斉研修を全くしていないにも関わらず,スキルが上達していくのは学年リーダを中心とした日常的なサポート体制が充実している証拠だと言える。
また年度末に行った最終調査では,(1)日常使うスキル(ワープロ,表計算,インターネットなど)が習得できた項目は100%,(2)ITを活用して授業ができるという項目は85%となった。

▲職員の意識調査 |
|
|
 |
| 6.急ぐのはソフト(人的支援)の整備 |
情報教育にしてもIT活用にしても,それを扱うのは人である。どんなにハード(機器)が整備されても,その機器の向こうには必ず人(ソフト)がいるという視点に立ち,ティーチングではなくコーチングによって職員の活用の意欲が高まるように対応した。
次のような例がある。ある時学年の4クラスで一斉にプレゼンを活用しながら人権学習をすることになった。パワーポイントも初めてならば,プロジェクタを使った授業なんて皆無の教師が2人。1人は昨年少し使ったことがある。そして使うことは負担ではない私の4人。初心者の2人は使わなければならないという不安が絶えずあった。しかし,前日に教室でリハーサルをするというので付き合った。ただしセッティングには手を出していない。ただいるだけである。雑談をしながら準備をし,「大丈夫そうですね!」の一言だけ。
当日はうまくいったかどうかは職員室に帰ってくるときの表情である程度わかった。二人とも笑顔だった。その後この二人は積極的にプロジェクタを使って授業を工夫するようになった。
またこのような例もある。新採用の社会科の教師はIT活用にも関心があるようだったので,自作した理科のプレゼンを見せた。「これどう?」とさりげなく。しばらくしてそのプレゼンをヒントに社会の授業用のプレゼンを作りたいと食い付いてきた。彼もパワーポイントは初めてだったが,すぐに授業で使うプレゼンを組み上げた。操作でわからないことだけはフォローしたが,あとはとにかく楽しみながらやっていると私の目には映った。
何も特別な方法をとったわけではない。とにかく初めての人には寄り添い,少ない口数でポイントだけをフォローする。それだけである。
デパートで「何かお探しですか」と店員につきまとわれたり,「これが春の新作なんです。お客さんにもお似合いかと思いますよ」と営業トークで欲しくもない商品を勧められたりする。それと同じようにパソコンおたくよろしく専門用語を並べて教えたり,聞いてもいないことまであれこれ教えようとする。こんなことをすれば,瞬く間に意欲の炎は鎮火してしまう。
教師はそれぞれ自分が目指そうとしている授業イメージがある。その中にITを活用した授業もあるだろう。しかし,ハード面での不安が理想とする授業への障壁となる。それを越えるために自己解決するまで寄り添うことでまた一人実践者が増えるのである。不安が安心に変わり,不満が満足に変わるのである。
最後に。ITを活用し始めた20代の教師から次のような言葉を聞いたことがある。「教材研究が楽しい。それにプレゼンをするときは,何を見せたらいいのか,何を話せばいいのか,今まで以上に考えるようになった。」まさに授業改善である。授業イメージがしっかりできてきている。そんな教師の授業では,生徒の顔がしっかりと上がっていた。
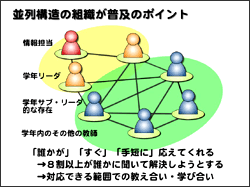
▲普及ポイント |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
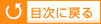 |
|
 |
 |
 |