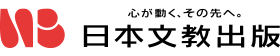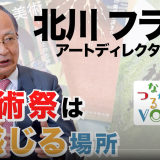ここがポイント
学びのロマンって何だろう
国語の先生は「学びのロマン」と名付けていたようですが、もしそのような概念があるとしたら、いったいどういったものだと理解したらいいでしょう。名前はどうであれ評価の核心に近づくもののような気がします。では少しずつ解き明かしてみましょう。
「学びのロマン」を内包する教育とは、子どもたちが自分の力で生きて行く力を身に着け、自己の未来を切り開き、幸せに生きて行くための教育と仮定してみるとどうでしょう。そのためには子どもたち自身がその授業の学びに価値を見出している必要があります。そのように考えると「育てたい3つの資質・能力」の内容と似通ってくる気はしませんか? 高い能力を得るための3つの資質・能力という考え方ではありません。子どもたち自身が自分たちの価値観でそのような能力を自然と求め、育もうとする姿を見取ることができるということが「学びのロマン」ということじゃないでしょうか。
子どもたちは授業中、「生きる力」や「未来を切り開いていく力」を育てるんだと思いながら学んではいません。もしそうであったならこれこそ得点のための学習ということになってしまいます。「能力」が少しずつ身に付き物事の感じ方や捉え方が変化していくに従い、徐々に「資質」も変化していきます。能力に比べ資質の変化はわずかずつでゆっくりです。ですが、教師が彼らの成長を見逃さず認め、肯定感を子どもたちと共有することこそ評価のコアといえそうです。
評価と評定
教師は高い位置から見下ろすかのように子どもたちを評価すべきではありません。教師と子どもたちが共有できる評価は、教師と子どもたちとの関係性、毎日行われる授業の中から生まれるのです。評価するポイントは教科の目標から派生する「内容のまとまり」等に言葉として示されていますが、その言葉をそのまま現場の評価に結び付けるのは、とても難しいことです。では一体どうすれば評価しやすいのでしょう。それは学習指導要領の文言を、一度目の前の子ども一人ひとりの姿に置き換えイメージしてみるのです。そして教師自らもその一員として等身大で評価の対象とするのです。飾らない普段の姿勢で子どもたちの成長や変化を見つけてみましょう。そこで大切なこととは、肯定感をもって育てるんだという温かさをもって見るということです。そのような見方をすると、うまく展開できなかった授業は、イメージの中では「それは先生がいけなかったんじゃないか」と子どもたちに叱られる場面も出てくるかもしれませんね。そうです、指導と評価は教師にも突きつけられる表裏一体なものなのです。
評価はその熱気を変化させ、冷静さとともに総括という過程を経て評定へと昇華されます。
授業の過程で見て取った状況把握の記録こそ総括への資料です。A・B・Cという記号は、感心し、認め、励ます記号です。それをもとに5段階の評定を導き出しましょう。冷静さの中で測られますが温かさを失わず、子どもたちには可能性を感じさせられるものにしたいですね。
(シナリオ・監修、文 川合 克彦)