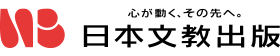ここがポイント
試験が知識なのか
今回登場した男子生徒二人の会話を振り返ってみましょう。そこから見えてくる試験勉強は授業中に記録した各自のノートの記述を暗記することであったようです。ですから定期試験は彼らにとってまるで蓄えた記憶をテスト用紙にばらまいたかのようでした。残念ながら二人にとって今回の美術の試験はあまり実りの多いものになっていなかったようです。試験終了後、生徒たちが気にするのは「何点だった?」という結果です。テストの出来を点数化するわけですから仕方のないことかもしれませんが、自分が学んだことにどのような意味があり、今後どう学習すればよいのかという、評価本来の働きが希薄になっている点が残念です。ですから教師の評価に対するあるべき取り組みが必要になってくるのです。評価は生徒たちの現状を理解し、それを暖かく認め、今後の学習の方向性や学習する意味、可能性を伝える大切な示唆でなくてはなりません。
本来テストで測りたかった知識とはただ言葉を暗記したものではなく、表現や鑑賞といった造形活動を通して生徒たちが対象から感じ取った感情に裏打ちされた知識だったのです。答案での答えは正解か否かを判断するのみでその答えの重さは授業の中で見取るしかありません。〔共通事項〕に示された内容を見てみましょう。教科全体を通して育んでいくべき美術科のコア(核)になる内容と言えます。
ア 形や色彩,材料,光などの性質や,それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
イ 造形的な特徴などを基に,全体のイメージや作風などで捉えることを理解すること。
知識・技能を評価することは他の評価の観点と比較して容易に思われますが、〔共通事項〕の指導内容を踏まえたものであるべきです。
二人が夕陽を見て、美術の学習したことと同期させることができたことは素晴らしかったですね。この二人には、美術の学びが根付いています。ぜひ授業でも評価したいものです。
(シナリオ・監修、文 川合 克彦)